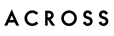コーネリアスになりたかった高校生
高校生の頃はミュージシャン志望でした。というよりはコーネリアス、小山田圭吾さんになりたかった。自分のやりたい音楽をやっていて、かつビジネスもできて、世界中にリスナーがいる。マニアックな部分をきちんと持っている一方でトラットリアというレーベルの活動もして、ファッションアイコンとしての面もある。いろいろな展開をしていて、必ずしもメジャーではなくても世界的な評価を受けているのに憧れてました。まあ高校生の自分がこんな言葉で語れたかどうかはともかく(笑)、こんなことを漠然と思っていました。
僕自身は、音楽や美術に興味があってそれを仕事にしていきたいけれども、食えないのは嫌なので、まず大学でビジネスを学んでからにしようと思い、一橋大学の商学部に入りました。
でもある時、曲を作っていてふと自分の曲がCDショップにあったとして、自分はこれを買うだろうか?と疑問に思ったんです。で、自分は曲作りは得意じゃないんだということが分かって、作曲したりミュ—ジシャンになるのは一度あきらめて、もうちょっとその業界そのものに関わって行こうかなと思うようになったんです。
ちょうどその頃は他にも美術とか文学とか、いろいろ他の分野にも興味が出てきた頃なんですが、自分はアーティストではなく、それを支える側にまわるんだろうな、と漠然と思っていましたね。それこそ自分でレーベルをやろうかな、とかそっちの方に興味が向くようになったんです。
ゼミでの専攻は「ブランド・マネジメント」だったんですが、そもそも“何かに付加価値をつけていくこと”に興味があったんです。例えば音楽を売る、とかもそうですけど、マーケットに対してどうしたら上手くやっていくかという技術。そのへんは編集にしてもブランディングにしてもあまり変わらないと思うんですけど、あるものをよく見せるために、どうやって価値付けをしていくかっていうことですね。若手の阿久津聡先生のゼミで、実際に企業や広告代理店と組んで、実際の企業や地域をテーマにしたブランディングを実際に行ったりしました。 平行して慶応のSFCの福田和也さんのゼミにもモグリで(笑)参加させてもらった。福田先生が当時持っていた小説と雑誌のゼミにも参加させていただき、小説の書き方、雑誌の作り方を勉強していました。あ、あと、後藤繁雄さんのやっていたスーパースクールにも通っていました。

学生の頃にお金を貯めて買ったギター

音楽から雑誌制作に
大学2年の時に雑誌を作る「super」という団体を立ち上げました。もともとフリーペーパーを作るサークルにも入っていたんですよ。作っていたのは学生向けの情報誌という感じのものだったんですが、自分ではカルチャー誌が作りたかったんです。当時自分が興味を持っていた音楽でもアートでも文学でも、雑誌という枠の中にだったら何でも入れることができるかなと。
「super」を立ち上げて、雑誌作りに向けて作業をしていたら、そのうちにどうやら「出版業界というものはいろいろと難しいらしい」とか「本というものはあんまり売れないらしい」とか「どうやら取次というやつに問題があるらしい」とか(笑)、いろんな業界に関する情報が入ってきますよね。で、出版業界というものはなかなか難しい状況になっているらしいということが判ってきた。ちょうど佐野慎一さんの「誰が本を殺すのか」がベストセラーになっていた頃なんですが、出版業界は難しい、でも同時に面白そうだ、とも思ったんです。
立ち上げようとしていたカルチャー雑誌は、結局発行しないまま終わってしまうんですが、構想としては、インターネット連動のカルチャー誌というものだったんですよ。見た目はアートブックで文字情報は殆どなく、1つ1つのグラフィックにURLがついていて、その先に行くと文字情報やフラッシュゲームがあるという仕組み。現在の環境であればもっと簡単にできていたかもしれませんが、当時の環境では厳しかったんですね。
その頃、青山ブックセンターに通って、週100冊くらい雑誌を読んでいたんですよ、すべて立ち読み(笑)。全部つまんないな、すげえ面白い雑誌作ってやる、って思ってました。もちろん情報として面白いっていうものはあったんですけど、なんかこうみんな同じフォーマットで、斬新だ!と感じさせてくれるようなものがなかったんです。当時面白いと思っていたのは野村訓市さんがIDEE(イデー)から出した『SPUTNIK』とか、ジョナサン・バーンブルックがアートディレクターをやっていた真四角の版の『広告』とか。インディペンデントな雰囲気が強かった頃の『TOKION』なんかも面白かったですね。
大学2年の時に雑誌を作る「super」という団体を立ち上げました。もともとフリーペーパーを作るサークルにも入っていたんですよ。作っていたのは学生向けの情報誌という感じのものだったんですが、自分ではカルチャー誌が作りたかったんです。当時自分が興味を持っていた音楽でもアートでも文学でも、雑誌という枠の中にだったら何でも入れることができるかなと。
「super」を立ち上げて、雑誌作りに向けて作業をしていたら、そのうちにどうやら「出版業界というものはいろいろと難しいらしい」とか「本というものはあんまり売れないらしい」とか「どうやら取次というやつに問題があるらしい」とか(笑)、いろんな業界に関する情報が入ってきますよね。で、出版業界というものはなかなか難しい状況になっているらしいということが判ってきた。ちょうど佐野慎一さんの「誰が本を殺すのか」がベストセラーになっていた頃なんですが、出版業界は難しい、でも同時に面白そうだ、とも思ったんです。
立ち上げようとしていたカルチャー雑誌は、結局発行しないまま終わってしまうんですが、構想としては、インターネット連動のカルチャー誌というものだったんですよ。見た目はアートブックで文字情報は殆どなく、1つ1つのグラフィックにURLがついていて、その先に行くと文字情報やフラッシュゲームがあるという仕組み。現在の環境であればもっと簡単にできていたかもしれませんが、当時の環境では厳しかったんですね。
その頃、青山ブックセンターに通って、週100冊くらい雑誌を読んでいたんですよ、すべて立ち読み(笑)。全部つまんないな、すげえ面白い雑誌作ってやる、って思ってました。もちろん情報として面白いっていうものはあったんですけど、なんかこうみんな同じフォーマットで、斬新だ!と感じさせてくれるようなものがなかったんです。当時面白いと思っていたのは野村訓市さんがIDEE(イデー)から出した『SPUTNIK』とか、ジョナサン・バーンブルックがアートディレクターをやっていた真四角の版の『広告』とか。インディペンデントな雰囲気が強かった頃の『TOKION』なんかも面白かったですね。

就職は3ヶ月で終了、フリー活動に
就職は、当時関心のあった本とかブランディングの勉強を生かした形でと考えていたんですが、既存の雑誌は全部つまらないって思っていたので、大手出版社に入ろうとは思いませんでした。むしろ出版業界全体を違う形で、俯瞰して見ることのできる所に行きたいと思ったんです。それでいろいろ考えた末に「東京国際ブックフェア」という本の見本市を主催している会社に入ったんです。出版業界を見るには変った場所だから面白そうだと思って。
当時はコンベンションという業種そのものが伸びていましたし。面接試験でも僕は「ブックフェアの仕事しかやりたくない」としか言わなかったんですが、それでも採用してもらった。で、ブックフェアを一度経験してすぐ辞めるんですよ。3ヶ月でした(笑)。
出版社に対してブースを売る仕事だったんですが、入社する前からブックフェアの仕事がしたいと自分で仕事選んでたわけですし、入社もすごく早く決まってたので、入った直後からすごい仕事振られるわけですよ。他の新入社員の倍くらい。僕はブックフェアを通してやりたいこと、やりたいと思えることにフォーカスしてその会社を選んでいたんですけど、仕事をする仲間や環境がいかに大事なのか、ということに気付いていなかったんですね。そこが大学生の浅はかなところで(笑)。
当時はちょうど「第2新卒」という言葉が流行するようになった頃で、その上限が25歳といわれていたんですが、だったら、それまでにいろいろ試してみて、25歳になっても食えないようなら改めて就職しようと思ったんです。25歳を超えても人から評価されるようなことが何もできていなかったら、そのときはもう就職もできないんだろうなって考えたんです。当時は就職氷河期とも言われていた頃で、厳しかったんですよ。その辺の自己評価はシビアでしたね。
会社を辞めてまず、文京区の千駄木にある「往来堂書店(おうらいどうしょてん)」で書店員のアルバイトを始めました。往来堂は町の小さな書店としてはとても有名なところで、後に「bk1」や「楽天ブックス」などの店長もつとめた安藤哲也さんが立ち上げたところです。そこに入れてもらった、といっても週に2〜3回、夕方からのアルバイトなんですけどね。
会社を辞めるときに考えていたのは、やっぱりどこか出版社とか取次とかに所属するのではなくて、その間にいるからこそできることは何かないだろうかと思っていました。業界が固まっていて、にっちもさっちもいかなくなっているような状態だからこそ、そのどこでもないところに、スキマでやれることがまだまだたくさんあるはずだと思ってました。で、それを探すためにまず新刊書店に入ったというわけです。
就職は、当時関心のあった本とかブランディングの勉強を生かした形でと考えていたんですが、既存の雑誌は全部つまらないって思っていたので、大手出版社に入ろうとは思いませんでした。むしろ出版業界全体を違う形で、俯瞰して見ることのできる所に行きたいと思ったんです。それでいろいろ考えた末に「東京国際ブックフェア」という本の見本市を主催している会社に入ったんです。出版業界を見るには変った場所だから面白そうだと思って。
当時はコンベンションという業種そのものが伸びていましたし。面接試験でも僕は「ブックフェアの仕事しかやりたくない」としか言わなかったんですが、それでも採用してもらった。で、ブックフェアを一度経験してすぐ辞めるんですよ。3ヶ月でした(笑)。
出版社に対してブースを売る仕事だったんですが、入社する前からブックフェアの仕事がしたいと自分で仕事選んでたわけですし、入社もすごく早く決まってたので、入った直後からすごい仕事振られるわけですよ。他の新入社員の倍くらい。僕はブックフェアを通してやりたいこと、やりたいと思えることにフォーカスしてその会社を選んでいたんですけど、仕事をする仲間や環境がいかに大事なのか、ということに気付いていなかったんですね。そこが大学生の浅はかなところで(笑)。
当時はちょうど「第2新卒」という言葉が流行するようになった頃で、その上限が25歳といわれていたんですが、だったら、それまでにいろいろ試してみて、25歳になっても食えないようなら改めて就職しようと思ったんです。25歳を超えても人から評価されるようなことが何もできていなかったら、そのときはもう就職もできないんだろうなって考えたんです。当時は就職氷河期とも言われていた頃で、厳しかったんですよ。その辺の自己評価はシビアでしたね。
会社を辞めてまず、文京区の千駄木にある「往来堂書店(おうらいどうしょてん)」で書店員のアルバイトを始めました。往来堂は町の小さな書店としてはとても有名なところで、後に「bk1」や「楽天ブックス」などの店長もつとめた安藤哲也さんが立ち上げたところです。そこに入れてもらった、といっても週に2〜3回、夕方からのアルバイトなんですけどね。
会社を辞めるときに考えていたのは、やっぱりどこか出版社とか取次とかに所属するのではなくて、その間にいるからこそできることは何かないだろうかと思っていました。業界が固まっていて、にっちもさっちもいかなくなっているような状態だからこそ、そのどこでもないところに、スキマでやれることがまだまだたくさんあるはずだと思ってました。で、それを探すためにまず新刊書店に入ったというわけです。

ネット古書店「ブックピックオーケストラ」を立ち上げる
平行してスタートしたのが「ブックピックオーケストラ」というネット古書店です。その頃ネット古書店がブームをちょっと過ぎようかという頃で、北尾トロさんの本が出たのもその頃です。ブックオフとアマゾン・マーケットプレイスを足して、そこから背取りをして売る、みたいなスタイルがサラリーマンのちょっとしたサイドビジネスみたいな形で注目されてた頃ですね。
これなら簡単にできそうかな、と思う一方で、ネット古書店は既に沢山あるという状態でしたからなんか変ったことやらないといけないなと思いまして。そこで、どうせそんなに儲からないものなら、名前を売るために目立つものにしようと思ったんです。
ブックピックオーケストラはまず3人で始めました。当時のネット古書店はサイドビジネスというか、“一人がなんとか食えるビジネス”だったので、あえて3人でやるという選択をしてそもそも従来のネット古書店のビジネスモデルでやっていくことを放棄したんです。雑誌をつくっていた時の経験からコンテンツを作れる人間はいるので、たった1冊の古本を売るのに、普通ではあり得ないくらい詳しく解説するとか、その本を持って街に出て、その街のどこかで写真を撮ってそのお店の紹介記事を書くとか、ほとんど雑誌みたいなことをウェブでやってみたんですよ。
ホームページには「古本屋ウェブマガジン ブックピックオーケストラ」とつけて、ネット古本屋なんだけどテキストサイトでもある、みたいな感じでスタートしました。まだ当時はブログがなかった時代ですからテキストサイトです。でも、ただテキストサイトを立ち上げても自分の知り合いくらいしかアクセスしませんけれど、ネット古書店という形でやっていると書名で検索した人がアクセスしたりするじゃないですか。それで、ふつうにテキストサイトをやっているよりはいろんな人の目に触れる、ということで、雑誌をやっていた頃の知り合いなどに声をかけて原稿を書いてもらったんです。
人に本の面白さを伝えるために、変ったこと、面白いことをやりながら、作品を作ったりクラブイベントで売ってみたりお店を出してみたりいろいろとやってみました。とにかく目立てば、道は開けると考えていたんです。変った商品を作って雑貨屋に卸したりもしましたね。文庫本を中身が見えないようにクラフト紙で包んで、片面は絵はがきのように宛名面にして、裏には本の中から引用した一部が書いてあるとか。
「文庫本葉書」といって1冊500円なんですけど、当然1つ1つ違いますから、引用文を見て選んでもらって、自分で開けるもよし、人にあげるもよし。そのまま切手を貼れば冊子小包として送ることもできるんですよ。これをクラブで売ったりして、結構ウケましたね。 そんなふうにスタートしてまだ間もないある日、北尾トロさんに声をかけていただいたんです。「最近立ち上がったみたいだけど面白そうなことやってるじゃない」と言っていただいて。で、北尾さんに誘っていただいて、3回目の「新世紀書店」というネット古書店のイベント(主催:北尾トロさん、会場:渋谷パルコ・ロゴスギャラリー)に「ブックピックオーケストラ」として参加したんです。
そのイベント「新世紀書店」に、コンセプトショップ「Tokyo Hipsters Club(トーキョー・ヒップスターズ・クラブ)」の担当者もたまたま来ていました。ビート系の本を扱うコーナーがちょっとだけあって、最初はそういう本を売って欲しいっていう話だったんですけど、話しているうちに、それは専門の担当者が必要だ、ということになり。新刊書も、和書も洋書も選んで、本の品揃えをコーディネートしてトータルで本の品揃えをして、とある種本屋的な業務が必要になってくるというはなしになったんです。「Tokyo Hipsters Club」は3階建てなんですが、その1階の、洋服と一緒に販売する書籍コーナーの担当者として、任されることになったんです。これがブックコーディネーターを名乗るようになった最初の仕事です。
平行してスタートしたのが「ブックピックオーケストラ」というネット古書店です。その頃ネット古書店がブームをちょっと過ぎようかという頃で、北尾トロさんの本が出たのもその頃です。ブックオフとアマゾン・マーケットプレイスを足して、そこから背取りをして売る、みたいなスタイルがサラリーマンのちょっとしたサイドビジネスみたいな形で注目されてた頃ですね。
これなら簡単にできそうかな、と思う一方で、ネット古書店は既に沢山あるという状態でしたからなんか変ったことやらないといけないなと思いまして。そこで、どうせそんなに儲からないものなら、名前を売るために目立つものにしようと思ったんです。
ブックピックオーケストラはまず3人で始めました。当時のネット古書店はサイドビジネスというか、“一人がなんとか食えるビジネス”だったので、あえて3人でやるという選択をしてそもそも従来のネット古書店のビジネスモデルでやっていくことを放棄したんです。雑誌をつくっていた時の経験からコンテンツを作れる人間はいるので、たった1冊の古本を売るのに、普通ではあり得ないくらい詳しく解説するとか、その本を持って街に出て、その街のどこかで写真を撮ってそのお店の紹介記事を書くとか、ほとんど雑誌みたいなことをウェブでやってみたんですよ。
ホームページには「古本屋ウェブマガジン ブックピックオーケストラ」とつけて、ネット古本屋なんだけどテキストサイトでもある、みたいな感じでスタートしました。まだ当時はブログがなかった時代ですからテキストサイトです。でも、ただテキストサイトを立ち上げても自分の知り合いくらいしかアクセスしませんけれど、ネット古書店という形でやっていると書名で検索した人がアクセスしたりするじゃないですか。それで、ふつうにテキストサイトをやっているよりはいろんな人の目に触れる、ということで、雑誌をやっていた頃の知り合いなどに声をかけて原稿を書いてもらったんです。
人に本の面白さを伝えるために、変ったこと、面白いことをやりながら、作品を作ったりクラブイベントで売ってみたりお店を出してみたりいろいろとやってみました。とにかく目立てば、道は開けると考えていたんです。変った商品を作って雑貨屋に卸したりもしましたね。文庫本を中身が見えないようにクラフト紙で包んで、片面は絵はがきのように宛名面にして、裏には本の中から引用した一部が書いてあるとか。
「文庫本葉書」といって1冊500円なんですけど、当然1つ1つ違いますから、引用文を見て選んでもらって、自分で開けるもよし、人にあげるもよし。そのまま切手を貼れば冊子小包として送ることもできるんですよ。これをクラブで売ったりして、結構ウケましたね。 そんなふうにスタートしてまだ間もないある日、北尾トロさんに声をかけていただいたんです。「最近立ち上がったみたいだけど面白そうなことやってるじゃない」と言っていただいて。で、北尾さんに誘っていただいて、3回目の「新世紀書店」というネット古書店のイベント(主催:北尾トロさん、会場:渋谷パルコ・ロゴスギャラリー)に「ブックピックオーケストラ」として参加したんです。
そのイベント「新世紀書店」に、コンセプトショップ「Tokyo Hipsters Club(トーキョー・ヒップスターズ・クラブ)」の担当者もたまたま来ていました。ビート系の本を扱うコーナーがちょっとだけあって、最初はそういう本を売って欲しいっていう話だったんですけど、話しているうちに、それは専門の担当者が必要だ、ということになり。新刊書も、和書も洋書も選んで、本の品揃えをコーディネートしてトータルで本の品揃えをして、とある種本屋的な業務が必要になってくるというはなしになったんです。「Tokyo Hipsters Club」は3階建てなんですが、その1階の、洋服と一緒に販売する書籍コーナーの担当者として、任されることになったんです。これがブックコーディネーターを名乗るようになった最初の仕事です。

ブックコーディネーターの面白さ
僕はブックコーディネーターという仕事は、お店とか空間のブランディングだ、と表現しているんです。それは、例えば内装の一部として1枚の絵を飾るよりも本棚を1つ置いた方がいい場合もある、ということなんです。このお店はこういうコンセプトです、っていうことを料理だったり洋服だったり、あるいは内装やかける音楽でテイストを作るわけですが、ただ単にこうセレクトショップにしても、カフェにしても実際には似通ったものが多くてなかなか差別化することは難しい。
そういう中で、本棚っていうのは「コンセプトそのものを言葉で伝えてもおかしくないもの」なんですよ。たとえばロックをコンセプトにした店の壁に大きく「ROCK」って書いてあったらかっこ悪いじゃないですか。でも本棚の中に「ROCK」と書いた本があってもおかしくない。しかも世界にはありとあらゆるテーマの本が存在するので、本棚というのは、すごく厳密かつ自然にコンセプトを表現できるメディアなんですよ。言葉そのものだけどインテリアにもなり得るというのは他にないなということに気付いたんです。
本を売るにしても閲覧するにしても、それを見せるということを通じてその空間をブランディングする。これはやってみてもっと需要があるな、と思うようになりました。「Tokyo Hipsters Club」を立ち上げてみたら、このショップを運営するワールドさんの他のショップからも依頼がありましたし、他のファッションブランドやカフェなどからも依頼が来るようになったんです。それで「ブックコーディネーター」としてやっていけるな、という感じになってきたところです。
アパレルショップは明確にまずブランドコンセプトがしっかりあって、それが言葉やイメージになっています。その背後にあるカルチャーとか、それを作ってきた歴史とか、過去のものであればそこと現在との接点とか、そういったものを僕は捉えて、ではこういう切り口はどうでしょうか、ということを提案するわけです。もちろん、向こうからもこれを置いてみてはどうか、という要望が出たりします。そういうやり取りをして、最終的に発注した本をどのようにして並べればいいかを考える。その全ての過程が僕はやっていて楽しいですし、向いていると思いますね。
僕と同じような仕事をしている人は他にもいると思うんですけど、それぞれ専門があるんですよね。こういうジャンルが得意、とか。そもそも得意ジャンルの古書店をやっている方が、そういうジャンルのイメージにしたいお店から声をかけられたり、というケースが多いと思うんです。でも、僕はあまり専門とか得意なジャンルというのを決めないようにしているんです。むしろジャンルは何でもいい。ワールドさんの中でも現在3ブランドのショップでブックコーディネートをしていますがジャンルもコンセプトも全然違うものです。ブランディングを広告代理店の担当者が考えるのと基本的には同じ作業なんです。
セレクトショップでも以前から洋書のビジュアルブックなどが並ぶようになっていましたが、それはショップのブランドの中で品揃えとしてふさわしいものを選んでいたと思うんです。今度はそこから進んで、そこから文化を発信していかなきゃいけないだろうという時に、もっとちゃんとした、背後にしっかりしたもののある、骨太の本、しかも結構大量のものが必要になってくるんですよ。
飾りとして、ちょっと関連のあるビジュアルブックが洋服の隣に置いてある。そういうことも大切だと思うんですけど、それはとてもたくさんの本棚の中から選ばれたものが置いてあるからこそ重みが違ってくると思うんです。そのお店独自のもの、つまりそれはブランドと言えるんですが、お店それぞれが持っている個性や思想を、それぞれのお店がもっと発信していかなきゃいけないだろうと思うんです。そういう意味で、本棚を持っているということは思想そのものを持っているということになるというわけです。
僕はブックコーディネーターという仕事は、お店とか空間のブランディングだ、と表現しているんです。それは、例えば内装の一部として1枚の絵を飾るよりも本棚を1つ置いた方がいい場合もある、ということなんです。このお店はこういうコンセプトです、っていうことを料理だったり洋服だったり、あるいは内装やかける音楽でテイストを作るわけですが、ただ単にこうセレクトショップにしても、カフェにしても実際には似通ったものが多くてなかなか差別化することは難しい。
そういう中で、本棚っていうのは「コンセプトそのものを言葉で伝えてもおかしくないもの」なんですよ。たとえばロックをコンセプトにした店の壁に大きく「ROCK」って書いてあったらかっこ悪いじゃないですか。でも本棚の中に「ROCK」と書いた本があってもおかしくない。しかも世界にはありとあらゆるテーマの本が存在するので、本棚というのは、すごく厳密かつ自然にコンセプトを表現できるメディアなんですよ。言葉そのものだけどインテリアにもなり得るというのは他にないなということに気付いたんです。
本を売るにしても閲覧するにしても、それを見せるということを通じてその空間をブランディングする。これはやってみてもっと需要があるな、と思うようになりました。「Tokyo Hipsters Club」を立ち上げてみたら、このショップを運営するワールドさんの他のショップからも依頼がありましたし、他のファッションブランドやカフェなどからも依頼が来るようになったんです。それで「ブックコーディネーター」としてやっていけるな、という感じになってきたところです。
アパレルショップは明確にまずブランドコンセプトがしっかりあって、それが言葉やイメージになっています。その背後にあるカルチャーとか、それを作ってきた歴史とか、過去のものであればそこと現在との接点とか、そういったものを僕は捉えて、ではこういう切り口はどうでしょうか、ということを提案するわけです。もちろん、向こうからもこれを置いてみてはどうか、という要望が出たりします。そういうやり取りをして、最終的に発注した本をどのようにして並べればいいかを考える。その全ての過程が僕はやっていて楽しいですし、向いていると思いますね。
僕と同じような仕事をしている人は他にもいると思うんですけど、それぞれ専門があるんですよね。こういうジャンルが得意、とか。そもそも得意ジャンルの古書店をやっている方が、そういうジャンルのイメージにしたいお店から声をかけられたり、というケースが多いと思うんです。でも、僕はあまり専門とか得意なジャンルというのを決めないようにしているんです。むしろジャンルは何でもいい。ワールドさんの中でも現在3ブランドのショップでブックコーディネートをしていますがジャンルもコンセプトも全然違うものです。ブランディングを広告代理店の担当者が考えるのと基本的には同じ作業なんです。
セレクトショップでも以前から洋書のビジュアルブックなどが並ぶようになっていましたが、それはショップのブランドの中で品揃えとしてふさわしいものを選んでいたと思うんです。今度はそこから進んで、そこから文化を発信していかなきゃいけないだろうという時に、もっとちゃんとした、背後にしっかりしたもののある、骨太の本、しかも結構大量のものが必要になってくるんですよ。
飾りとして、ちょっと関連のあるビジュアルブックが洋服の隣に置いてある。そういうことも大切だと思うんですけど、それはとてもたくさんの本棚の中から選ばれたものが置いてあるからこそ重みが違ってくると思うんです。そのお店独自のもの、つまりそれはブランドと言えるんですが、お店それぞれが持っている個性や思想を、それぞれのお店がもっと発信していかなきゃいけないだろうと思うんです。そういう意味で、本棚を持っているということは思想そのものを持っているということになるというわけです。

やはり僕は本の面白さを伝えていきたい
仕事と離れた僕個人のモチベーションとしては、大学時代に佐野慎一さんの本を読んでいた頃から考えていたことですが、本が売れないとか、若い人の活字離れとか、そういうことを僕もなんとかしたいと思っていて、それも現在の仕事をしている理由の1つだと考えているんです。たとえば洋服にしか興味がない人に対して、そのファッションはどこから来ているのか、ってことを、こういうお店だったら本を媒介にして伝えることができるわけです。
今の日本では、自分がどういう服を着るかということと、自分の思想が切り離されていて、そういう状態で服を着てもカッコよくない。だからこうして洋服屋の中に本棚があって、お客さんに何かを伝えるということには凄く意味があるんだということを言われたんですよ。
僕ができることは、ふだん本を読まないような人がお店にやってきて、中に入ってみたら本が積んであったりして、なんかちょっとカッコいいな、というくらいの気持ちで服や雑貨といっしょに文庫本でもいいから買ってもらって、読んでみたら面白いと感じてもらえたらいいなと。それで次は本屋に行ってみるとか、またこの店に来てくれるとか。本などあまり読まなかった人がちょっとでも本の面白さに気付いてもらえるようになればそれでいい。本の面白さを、アパレルだったらファッション好きの人に、カフェだったらカフェ巡りが好きな人に、ちょっとでも知らせることができればいいな、というのが、ブックコーディネーターとしての僕の一貫したモチベーションになっています。
例えばものをつくっている人、ファッションデザイナーと呼ばれる人たちは、まあ当たり前なんですけど着ている人よりもいろんなことを考えているわけですよね。でも意外に着ている人はそんな作り手の思いには気付いていない。それをきちんとお客様に伝えられるようにスタッフ教育でカバーすることも必要だと思いますけど、1冊「この本もいっしょに売ってね」と指示するだけでも何か伝わるかもしれない。ここでも実際にお店のスタッフが読んでくれたりということがある。そもそもブランド論では、組織の内側に対するブランディングも、とても重要な要素と考えられています。中で働いている人にブランドを知ってもらうことが、そのままそのブランドそれ自体になっていく。
ある老舗ブックカフェのオーナーが言われていたことなんですが、「ブックカフェは得てしてカフェか本屋のどちらかになってしまう」。実際に見ているとそうなんですよね。なんでかよく判らないのですが、ブックカフェって日本では根付いていないんです。実はカフェと本屋っていうのは、思っているよりも相性がよくないんじゃないかという気がしているんです。むしろアパレルの方が合っているんじゃないかと思いますね。
文化を伝える、ということで本というものは役に立つと思っていて、そう考えるとアパレルはきちんとブランドというものを伝えていくという必要がそもそもの業態にある。そういうものにくっついていく方が本は向いているんです。そう考えると現時点でカフェにはあまりその必要がないというか、カジュアルなカフェの場合は特にいまのところ、オーナーもそれほどブランディングというものを必要としていない。そう考えると、実はカフェには本によるブランディングの必要はあまりないのではないかと。カフェの場合はお店に入ることのできる人数も限られていますし、それってブランディングというよりもサービスになってしまうんです。
「本のメルマガ」というメールマガジンでも書いているんですが、出版業界の人ってウェブのことを概してよく知らない。ウェブを知らない出版業界の人に向けてウェブで起こっていることを伝える、というのもぼくの使命のひとつかなと思っているんです。出版にとってのウェブって、合わせたり差別化したり組んだりとかいろんなことをいちばんしていかなくてはいけない相手であることは間違いないので、その助けをするのも僕の仕事の1つだと考えています。
仕事と離れた僕個人のモチベーションとしては、大学時代に佐野慎一さんの本を読んでいた頃から考えていたことですが、本が売れないとか、若い人の活字離れとか、そういうことを僕もなんとかしたいと思っていて、それも現在の仕事をしている理由の1つだと考えているんです。たとえば洋服にしか興味がない人に対して、そのファッションはどこから来ているのか、ってことを、こういうお店だったら本を媒介にして伝えることができるわけです。
今の日本では、自分がどういう服を着るかということと、自分の思想が切り離されていて、そういう状態で服を着てもカッコよくない。だからこうして洋服屋の中に本棚があって、お客さんに何かを伝えるということには凄く意味があるんだということを言われたんですよ。
僕ができることは、ふだん本を読まないような人がお店にやってきて、中に入ってみたら本が積んであったりして、なんかちょっとカッコいいな、というくらいの気持ちで服や雑貨といっしょに文庫本でもいいから買ってもらって、読んでみたら面白いと感じてもらえたらいいなと。それで次は本屋に行ってみるとか、またこの店に来てくれるとか。本などあまり読まなかった人がちょっとでも本の面白さに気付いてもらえるようになればそれでいい。本の面白さを、アパレルだったらファッション好きの人に、カフェだったらカフェ巡りが好きな人に、ちょっとでも知らせることができればいいな、というのが、ブックコーディネーターとしての僕の一貫したモチベーションになっています。
例えばものをつくっている人、ファッションデザイナーと呼ばれる人たちは、まあ当たり前なんですけど着ている人よりもいろんなことを考えているわけですよね。でも意外に着ている人はそんな作り手の思いには気付いていない。それをきちんとお客様に伝えられるようにスタッフ教育でカバーすることも必要だと思いますけど、1冊「この本もいっしょに売ってね」と指示するだけでも何か伝わるかもしれない。ここでも実際にお店のスタッフが読んでくれたりということがある。そもそもブランド論では、組織の内側に対するブランディングも、とても重要な要素と考えられています。中で働いている人にブランドを知ってもらうことが、そのままそのブランドそれ自体になっていく。
ある老舗ブックカフェのオーナーが言われていたことなんですが、「ブックカフェは得てしてカフェか本屋のどちらかになってしまう」。実際に見ているとそうなんですよね。なんでかよく判らないのですが、ブックカフェって日本では根付いていないんです。実はカフェと本屋っていうのは、思っているよりも相性がよくないんじゃないかという気がしているんです。むしろアパレルの方が合っているんじゃないかと思いますね。
文化を伝える、ということで本というものは役に立つと思っていて、そう考えるとアパレルはきちんとブランドというものを伝えていくという必要がそもそもの業態にある。そういうものにくっついていく方が本は向いているんです。そう考えると現時点でカフェにはあまりその必要がないというか、カジュアルなカフェの場合は特にいまのところ、オーナーもそれほどブランディングというものを必要としていない。そう考えると、実はカフェには本によるブランディングの必要はあまりないのではないかと。カフェの場合はお店に入ることのできる人数も限られていますし、それってブランディングというよりもサービスになってしまうんです。
「本のメルマガ」というメールマガジンでも書いているんですが、出版業界の人ってウェブのことを概してよく知らない。ウェブを知らない出版業界の人に向けてウェブで起こっていることを伝える、というのもぼくの使命のひとつかなと思っているんです。出版にとってのウェブって、合わせたり差別化したり組んだりとかいろんなことをいちばんしていかなくてはいけない相手であることは間違いないので、その助けをするのも僕の仕事の1つだと考えています。
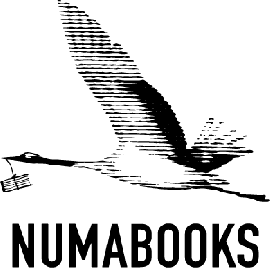
個人レーベル「NUMABOOKS」
こういった仕事をしていくための“個人レーベル”として「NUMABOOKS」を立ち上げました。ブックコーディネートをメインに活動していましたが、徐々にブランディングであったりクリエイティブディレクションだったりアイデア出しだったりに、業務がひろがってきました。
ブックピック・オーケストラは現在任意団体というかたちをとっていますが、一時期はNPOにしようと考えていました。それで食べているわけではなく、他に仕事もある人たちが集まって活動しています。実際に、ちょっとでも関わったりしてもらった方を含めると既に何十人というメンバーがいるので、いっしょに楽しくやっていくことをテーマにして、個人の仕事とは切り離しています。
元々僕が本に興味を持ったのは、いろんなものの受け皿になるから。僕自身は音楽も映画もファッションも文学もなんでも好きなので、それが全部入る入れ物として好きなんです。なので、逆に「NUMABOOKS」で本じゃない仕事をしても、本というものには何でも入るんだよ、ということで本というものの面白さを伝えて行くことにつながると思っています。
その「入れ物」としての本自体も面白くしていかなくてはいけないし、中身も当然面白くなくてはいけない。音楽、映画ひいては社会そのものだったり日本や世界そのものが面白くないと本も面白くないわけですから、本を入り口としたいろんなことを面白くしていくことが、小さいながらもやってければいいなと思ってます。
現在僕が携わっている仕事の1つに、ホテルでのブックコーディネートがあります。リゾート地のホテルのロビーなんですが、本当にやりたいのは客室ですね。ホテルの部屋にはちゃんとした机もあるのに、中から出てくるのは聖書とホテルの案内くらいで、案外活字が少ないんですよ。ちょっと高いクラスの部屋だったら本棚があって、その土地に関する本や名作なんかがあって、夜暇な時なんかに読んでもらえたら、例えば高級な油絵を飾るよりもよっぽどいいと思うんですけどね。いい部屋だったら、別にアメニティとして持って帰ってもらうくらいのつもりで置いてあげればいいんじゃないでしょうか。
最近は、なるべく仕事のジャンルが固まらないように、むしろ意識して散らしているようなところがあります。例えば今度食品のブランディングの依頼も受けているんですよ。「アイデア一発出し」「何かいいこと言う」みたいなのはもともと得意なんです(笑)。「アイデア・プランナー」として取り組んでいる仕事ですね。他には女性向けポータルサイトの企画なんかも書いたり。結局「よく伝える」「あるものをどう使ったら面白くなるか」「どう組み合わせたら新しく伝わるか」ということが好きだし、これからも携わって行きたいと思っています。
今度事務所を兼ねて会員制のカフェというかサロンみたいなものを作ろうと思っているんです。シェアオフィスのような形にして、カフェっぽい雰囲気の共有スペースで普段は会議室替わりにも使いながら、そこでイベントもできる、というような空間をオープンしようと思っています。
こういった仕事をしていくための“個人レーベル”として「NUMABOOKS」を立ち上げました。ブックコーディネートをメインに活動していましたが、徐々にブランディングであったりクリエイティブディレクションだったりアイデア出しだったりに、業務がひろがってきました。
ブックピック・オーケストラは現在任意団体というかたちをとっていますが、一時期はNPOにしようと考えていました。それで食べているわけではなく、他に仕事もある人たちが集まって活動しています。実際に、ちょっとでも関わったりしてもらった方を含めると既に何十人というメンバーがいるので、いっしょに楽しくやっていくことをテーマにして、個人の仕事とは切り離しています。
元々僕が本に興味を持ったのは、いろんなものの受け皿になるから。僕自身は音楽も映画もファッションも文学もなんでも好きなので、それが全部入る入れ物として好きなんです。なので、逆に「NUMABOOKS」で本じゃない仕事をしても、本というものには何でも入るんだよ、ということで本というものの面白さを伝えて行くことにつながると思っています。
その「入れ物」としての本自体も面白くしていかなくてはいけないし、中身も当然面白くなくてはいけない。音楽、映画ひいては社会そのものだったり日本や世界そのものが面白くないと本も面白くないわけですから、本を入り口としたいろんなことを面白くしていくことが、小さいながらもやってければいいなと思ってます。
現在僕が携わっている仕事の1つに、ホテルでのブックコーディネートがあります。リゾート地のホテルのロビーなんですが、本当にやりたいのは客室ですね。ホテルの部屋にはちゃんとした机もあるのに、中から出てくるのは聖書とホテルの案内くらいで、案外活字が少ないんですよ。ちょっと高いクラスの部屋だったら本棚があって、その土地に関する本や名作なんかがあって、夜暇な時なんかに読んでもらえたら、例えば高級な油絵を飾るよりもよっぽどいいと思うんですけどね。いい部屋だったら、別にアメニティとして持って帰ってもらうくらいのつもりで置いてあげればいいんじゃないでしょうか。
最近は、なるべく仕事のジャンルが固まらないように、むしろ意識して散らしているようなところがあります。例えば今度食品のブランディングの依頼も受けているんですよ。「アイデア一発出し」「何かいいこと言う」みたいなのはもともと得意なんです(笑)。「アイデア・プランナー」として取り組んでいる仕事ですね。他には女性向けポータルサイトの企画なんかも書いたり。結局「よく伝える」「あるものをどう使ったら面白くなるか」「どう組み合わせたら新しく伝わるか」ということが好きだし、これからも携わって行きたいと思っています。
今度事務所を兼ねて会員制のカフェというかサロンみたいなものを作ろうと思っているんです。シェアオフィスのような形にして、カフェっぽい雰囲気の共有スペースで普段は会議室替わりにも使いながら、そこでイベントもできる、というような空間をオープンしようと思っています。

インタビューユニットを構想中!
ずっと暖めていてまだ少しづつ始めたばかりのところなんですけど、インタビューって面白いなと。されながら言うのもどうかと思うんですけど(笑)。
写真家とインタビュアーってある部分で似ているじゃないですか。写真は対象となる人をどう撮るか、という技術であって、インタビューはその人の言葉をどう捉えるかというのが技術です。でもモデルを募集して「この写真家に撮ってもらいたい」という人がたくさん集まる有名なカメラマンはたくさんいますけど、「このインタビュアーに聞いてもらいたい」という人がたくさん集まる有名なインタビュアーというのは、なぜあまりいないのだろうと。で、その理由の1つは、写真には評論はあっても、インタビュー評論というものがないでしょう。インタビュアーの善し悪しについてはあまり意識されない。インタビュアーという職業自体があまり名前が出てくるようなものじゃないということなのかもしれないですけど、インタビューというものの技術そのものもあまりまとめられていないような気がします。で、僕も仕事で人にインタビューすることがあるからなんですが、インタビューというものについてちゃんと考えて、その月に出た雑誌のインタビューを見て「今月はこのインタビューがよかった!」と言い合うような団体をまずはサークルレベルでいいから作りたいなと思いまして。
インタビュアーの仕事って、ライターとは似ているようで微妙に違うと思うんですよね。で、今月はこのインタビューがよかった」「ここでこの質問はないだろう」なんて言い合ったりして、ひいては切磋琢磨したいなというのが1つ。もう1つはインタビューユニットというのが見た目としていたら面白いなと思ったんですよね。これは実際にやろうと思ってるんですが、街角で似顔絵屋みたいにインタビュー屋をやろうとか。実際に公園とかフリマとかでインタビューをして、後日それをテキストにして上げたりとか。その活動を続けていると、インタビューされたい人が来るじゃないですか。インタビューってやはり一発目が大切っていうか、最初にその人を見つけた感じっていうのが面白いと思うんですよね。面白い素材が向こうからインタビューをされに来るような場になったいいんじゃないかなと。
ふつうの人でもインタビューの技術次第で面白い話は引きだせると思うんです。例えばスタッズ・ターケルみたいな何百人/何千人に聞く、という手法がありましたけど、現在はウェブを使ったりしてまた違った展開が考えられんではないかと思います。それで、そのインタビューユニットに依頼が来たりすればいいなあと。インタビューという表現方法にはぜひ取り組んでみたいと思いますね。
ずっと暖めていてまだ少しづつ始めたばかりのところなんですけど、インタビューって面白いなと。されながら言うのもどうかと思うんですけど(笑)。
写真家とインタビュアーってある部分で似ているじゃないですか。写真は対象となる人をどう撮るか、という技術であって、インタビューはその人の言葉をどう捉えるかというのが技術です。でもモデルを募集して「この写真家に撮ってもらいたい」という人がたくさん集まる有名なカメラマンはたくさんいますけど、「このインタビュアーに聞いてもらいたい」という人がたくさん集まる有名なインタビュアーというのは、なぜあまりいないのだろうと。で、その理由の1つは、写真には評論はあっても、インタビュー評論というものがないでしょう。インタビュアーの善し悪しについてはあまり意識されない。インタビュアーという職業自体があまり名前が出てくるようなものじゃないということなのかもしれないですけど、インタビューというものの技術そのものもあまりまとめられていないような気がします。で、僕も仕事で人にインタビューすることがあるからなんですが、インタビューというものについてちゃんと考えて、その月に出た雑誌のインタビューを見て「今月はこのインタビューがよかった!」と言い合うような団体をまずはサークルレベルでいいから作りたいなと思いまして。
インタビュアーの仕事って、ライターとは似ているようで微妙に違うと思うんですよね。で、今月はこのインタビューがよかった」「ここでこの質問はないだろう」なんて言い合ったりして、ひいては切磋琢磨したいなというのが1つ。もう1つはインタビューユニットというのが見た目としていたら面白いなと思ったんですよね。これは実際にやろうと思ってるんですが、街角で似顔絵屋みたいにインタビュー屋をやろうとか。実際に公園とかフリマとかでインタビューをして、後日それをテキストにして上げたりとか。その活動を続けていると、インタビューされたい人が来るじゃないですか。インタビューってやはり一発目が大切っていうか、最初にその人を見つけた感じっていうのが面白いと思うんですよね。面白い素材が向こうからインタビューをされに来るような場になったいいんじゃないかなと。
ふつうの人でもインタビューの技術次第で面白い話は引きだせると思うんです。例えばスタッズ・ターケルみたいな何百人/何千人に聞く、という手法がありましたけど、現在はウェブを使ったりしてまた違った展開が考えられんではないかと思います。それで、そのインタビューユニットに依頼が来たりすればいいなあと。インタビューという表現方法にはぜひ取り組んでみたいと思いますね。

何でもやりますよ、っていうスタンス
コレクター的な個人の本へのこだわりとか好きなジャンルももちろんありますよ(笑)。でもそれはそれというか、自分で「何でもやります」と言っている以上、自分の個人的な趣味に偏らないようにしています。色がついてしまって、そのジャンルの仕事に偏ってしまうのが嫌なんです。そこはブランディングをやっているので、コントロールしてます、ええ(笑)。あくまでも編集すること、見せる技術のほうにフォーカスしたいので、特定の文学とか音楽のジャンルの人、という感じでセグメントされたくないんです。
菊地成孔さんが言われてたことなんですけど、よく「いろいろなことをやってらっしゃいますね」って言われるけど自分の中では音楽も文章も実は自分の中では繋がっているんだと。僕にとっても、本を並べることも文章を書くことも、何かをよく見せるという点では1つなんです。これから音楽をやろうと思っているんですが、音楽をやる時でも多分やり方はそんなに変らなくて、そのやり方そのものを僕は自分らしさとしていきたいですし、それが自分なんだと言い切っていけばそれなりの力が出てくるのでは、と思います。「この人何やってる人なんだろう?」と思われるくらいの方が僕にとってはいいですね。
僕が今やっている仕事って、ちょっと前だったら“プロデューサー”と呼ばれたり名乗っていたのかもしれないんですが、僕は“プロデューサー”というのがちょっと恥ずかしい世代なんですよ。一番最初に知った“プロデューサー”が小室哲哉だった世代です(笑)。よっぽど偉くないとプロデューサーとは名乗れないなあ、という気恥ずかしさみたいなものがありますね。それよりもディレクションとかコーディネーションという方が身の丈や取り組んでいる仕事には合っているような気がします。同じように、コンサルティングっていう言葉にも気恥ずかしさを感じてしまいます。もちろん仕事によってはそう名乗らざるを得ないこともあるので、いずれ僕がプロデューサーとかコンサルタントを名乗っているのを見つけても責めないでいただきたいんですけどね(笑)。
[取材・文/本橋康治(フリーライター)]
[取材日時・場所:2007年5月22日(火)15:30-17:00@Tokyo Hipsters Club(渋谷)]
菊地成孔さんが言われてたことなんですけど、よく「いろいろなことをやってらっしゃいますね」って言われるけど自分の中では音楽も文章も実は自分の中では繋がっているんだと。僕にとっても、本を並べることも文章を書くことも、何かをよく見せるという点では1つなんです。これから音楽をやろうと思っているんですが、音楽をやる時でも多分やり方はそんなに変らなくて、そのやり方そのものを僕は自分らしさとしていきたいですし、それが自分なんだと言い切っていけばそれなりの力が出てくるのでは、と思います。「この人何やってる人なんだろう?」と思われるくらいの方が僕にとってはいいですね。
僕が今やっている仕事って、ちょっと前だったら“プロデューサー”と呼ばれたり名乗っていたのかもしれないんですが、僕は“プロデューサー”というのがちょっと恥ずかしい世代なんですよ。一番最初に知った“プロデューサー”が小室哲哉だった世代です(笑)。よっぽど偉くないとプロデューサーとは名乗れないなあ、という気恥ずかしさみたいなものがありますね。それよりもディレクションとかコーディネーションという方が身の丈や取り組んでいる仕事には合っているような気がします。同じように、コンサルティングっていう言葉にも気恥ずかしさを感じてしまいます。もちろん仕事によってはそう名乗らざるを得ないこともあるので、いずれ僕がプロデューサーとかコンサルタントを名乗っているのを見つけても責めないでいただきたいんですけどね(笑)。
[取材・文/本橋康治(フリーライター)]
[取材日時・場所:2007年5月22日(火)15:30-17:00@Tokyo Hipsters Club(渋谷)]