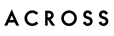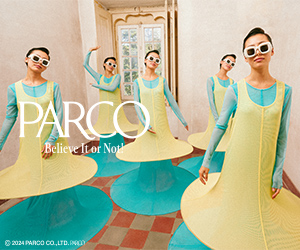●インスタグラムなどでショーの様子は消費者もほぼリアルタイムで見ることができるようになったのに買えるのはその6ヶ月後。その間に消費者は飽きてしまい、ファストファッションにコピーする時間を与えている。
●消費者はいまの気候に合うものを買うようになっているが、従来のモデルでは暖かい頃にコートを売り始める。冬本番にはディスカウントされて、小売側も売上をディスカウントに依存する不毛なサイクルに陥っている。
●オフシーズンのコレクションによってデザイナーは年中フル稼動を求められ、「クリエイティヴ・ディレクター」とは縁遠いマシンになり果てて消耗している。