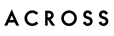10年間当たり前にやってきたことを、ローカルじゃないNYでやってみたかったんです。
服を作るようになって10年間、ずっと東京でコレクションを発表してきたのですが、去年の9月からコレクションをニューヨークで見せるようになりました。
第1回目のテーマは「ポリス・ピクチャー」で、プレゼンテーションという形態をとりましたが、今年2月には「ハーフ・ドーム」というタイトルをつけて、アンセル・アダムスのヨセミテ国立公園をテーマにしたコレクションを、ランウェイという形態で発表しました。
なんで今回はランウェイなんだってよく聞かれましたが、過去10年間当たり前にやってきたことをまたやったという感じです。NYではローカルじゃない自分たちがいて、限られた条件のなかでできることをやりたかった、それから、あえて「ニューヨークらしい」やり方で、服をメインに見せることを目指したショーでした。
東京だったらいろんな仕込みをすることによってテーマを伝えるランウェイをやる。でもNYでは、あえて舞台作りなどはいたってシンプルにしました。NYでやるようになって2度目、まだプロダクションチームとの関係もなかなか思うほどしっかりできていない状況で、自分の気持ちだけが先走って、できたものが完全でない、という状況になるのが不安だった。だったら音や光はシンプルにして、必要最低限のことで伝えられることに集中しました。
僕が思う「NYらしさ」っていうのは、いまだにブランド名がバックに入ったようなステージに、シンプルなライティング、そこにモデルがどんと出てdきて、メインは服を見せることだったり。つまりベタな感じもアリなんですね。そんななかに、僕らなりのテイストを足して、ローカルのデザイナーとは一味違うベタなNYスタイルを目指した。シンプルなランウェイに、バックは山肌をイメージしたパネルを立てて、光だけで見せるというやり方をした。
実は、ファッションショーのライティングの使い方という点では、日本って天才的なんです。東京でやってる限りは、材料もいっぱいあるし、ずっとやってきた分、業者さんとも関係ができていたから、大掛かりなことを格安でやってもらえたりするんですが、まったく同じことを、NYでやろうとすると、けっこうなお金がかかってしまう。まだローカルの業者との関係ができあがっていないから、僕らには無理なんです。だったらできることからやっていこうかなという自然な流れでした。
東京コレクションでは服はもちろんですが、どうやって見せるか、つまり椅子の高さひとつ、壁の質感、あとで説明しないと誰にも伝わらないようなことまで、すごく気にしていました。前回、初めてNYでプレゼンテーションをやってみて、「ここだったら、大味なやり方をしても、確実に伝えることができるバイブレーションを作り出せる」と思ったんです。
日本でやっている間は、シートの触り心地から何からとことん突き詰めていた。僕自身が細かいことに神経質になりすぎてたのかもしれません。もちろん、細かいこだわりは、大事なことだと思うんですが、前回のNYでそうじゃないことでも伝えられるという自信がつきました。やり過ぎないちょうど良い加減で、自分の見せたかったものを表現できたかなと思います。オーディエンスも服に集中してみてくれたし、満足しています。