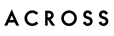日本国内ではあまり知られていないが、実は、日本のメンズファッションが海外のジャーナリストやバイヤーなどから評価されている。その代表的な存在ともいえるブランドのひとつが、「エンジニアド・ガーメンツ」だ。ベースにあるのは古き良き時代のアメリカ。現代風にアレンジされたその独特の風合いによる新しいアメリカン・カジュアルは、今でも主に30代以上のファッション通の間で熱烈なファンが多い。
興味深いのは、「Engineered Garments(エンジニアド・ガーメンツ)」は、NYで生まれ、企画からデザイン、生産までのすべてをアメリカで行っていることだろう。近年、アメリカのアパレルブランドの多くが中国や中南米などに生産拠点を移すなか、同ブランドは、あえてアメリカ国内の古い工場での伝統的な製法にこだわってきた。
そんななか、2008年には、メンズファッション誌「GQ」と米ファッションデザイナー評議会が設立した「第1回ベスト・ニューメンズウエアデザイナー・イン・アメリカ」に同ブランドのデザイナーの鈴木大器氏がグランプリを受賞。2010年には、同ブランドのルーツでもあるセレクトショップ「NEPENTHES(ネペンテス)」をオープン。
“MADE IN JAPAN”がある意味マーケティングのトレンドとなっている昨今、「日本人がプロデュースするMADE IN USA」というひとヒネリした活動を展開する鈴木さんにNY在住のライター佐久間裕美子さんがインタビューを行った。