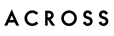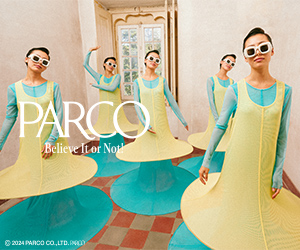2015年1月、長らく廃墟となっていた映画館がリノベを経て新しく名画座「The Projector(ザ・プロジェクター)」として生まれ変わった。
「都市再生」、「旧建築のリノベーション」、「(映画を通じた)コミュニティの再生」、「クラウドファンディング」。昨今の「都市論」のトレンドを凝縮したかのようなこのプロジェクト。実は日本の話ではなく、東京23区と同程度の面積の島に約550万人が暮らす都市国家シンガポールでの事例である。
「都市再生」、「旧建築のリノベーション」、「(映画を通じた)コミュニティの再生」、「クラウドファンディング」。昨今の「都市論」のトレンドを凝縮したかのようなこのプロジェクト。実は日本の話ではなく、東京23区と同程度の面積の島に約550万人が暮らす都市国家シンガポールでの事例である。
リー・クアン・ユー元首相の強力なリーダーシップの下、東南アジアのビジネスハブとして確固たる地位を築いた国シンガポールだが、カルチャー的な面白さという観点からは、まだまだ物足りないというのが東京からシンガポールに移り住んだ筆者の当初の感想だった。
しかし、よく目を凝らしてみると、シンガポールでもトレンドとなっている「自転車」や「サードウェーブコーヒー」などの潮流と呼応するように、小規模ではあるものの、カルチャーを盛り上げようというローカルかつインディーな取り組みが動き始めていることに気がついた。
「The Projector(ザ・プロジェクター)」はそうした流れを象徴する存在であり、今年1月にオープンして以来、トレンドに敏感な若者や外国人らの熱い支持を得ている。
シンガポールのカルチャーシーンに確実に何かが起こりつつあるのでは? そのヒントを探るべく、同プロジェクトを手がけたシンガポールの新進気鋭の開発コンサル企業Pocket Projects(ポケットプロジェクツ)のメンバーで、現在は同館長として運営業務を統括するSharon Tan(シャロン・タン)さんに話を伺った。